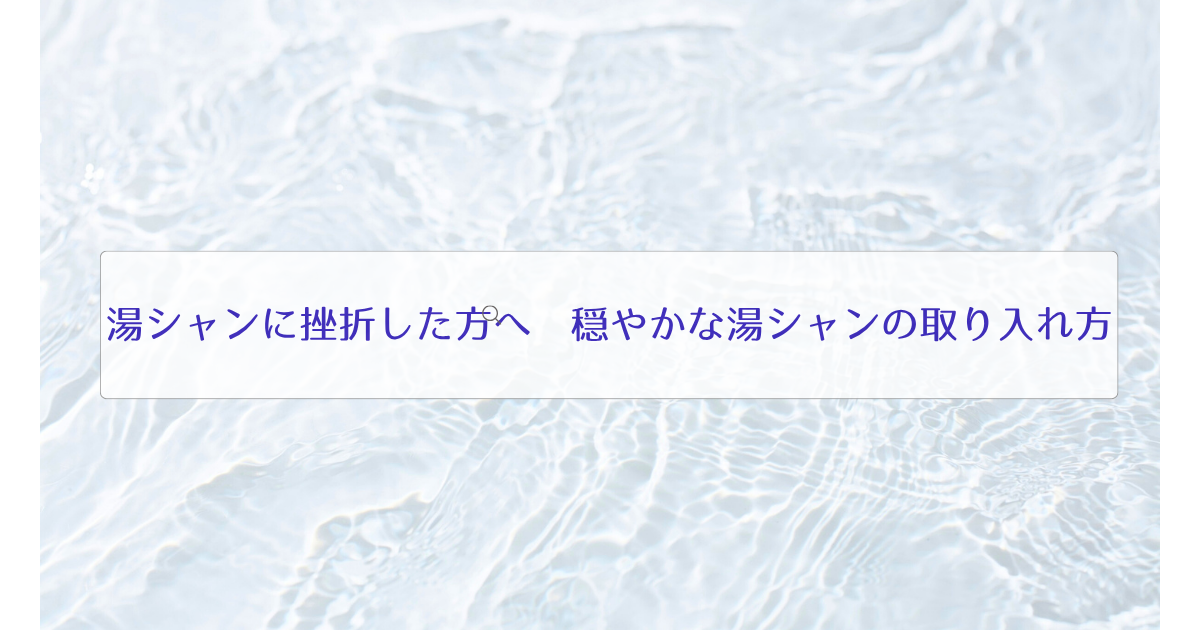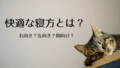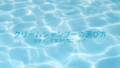こちらのブログでは、湯シャンに興味があるけどちょっとハードルが高く感じるなという方や、一度チャレンジ
してみたけど挫折してしまった、でも将来の髪や頭皮のことを考えたらやっぱり湯シャン良いような気がする
けど難しい〜と、湯シャンを取り入れたいんだけどなかなか難しいと感じている方に、自分なりのスタイルで
湯シャンの取り入れ方を見つけるための提案を、私の体験を元にさせていただきたいと思います。
湯シャンを取り入れるといっても、0か100かではなく、自分のスタイルに合わせて何を望んでいるのかを明確
にして、それぞれの湯シャンの取り入れ方を見つけてもらえれば、その参考になれば嬉しいです!
湯シャンのやり方とメリット・デメリット
やり方
①お風呂に入る前にブラッシングをして、髪のもつれを解いておきます。
頭皮や髪に付いた汚れを落としやすくしておく効果もあります。
②36〜39度の温度のシャワーで、頭皮マッサージをしながらお湯だけで頭皮を洗います。
5分くらいかけてしっかり洗いましょう。
③タオルで包み込むようにして、できるだけ摩擦を起こさないように水分を拭き取り、その後ドライヤーで
乾かします。
髪を保護する物を使っていないため、ドライヤーの熱にも注意しながら熱くなりすぎないように手早く
乾かします。
メリット
- 髪質、頭皮環境の改善
- カラーを入れている場合、退色を遅らせることができる
- 肌の弱い方にはシャンプートリートメントの刺激を避けることができる
- 抜け毛、薄毛の改善
私の感じるメリット
以上が、美容師の方や病院の先生などが話されているメリットをまとめたものです。
ちなみに、湯シャン実践者にアンケートを取られた方がいらっしゃって、そのアンケートによると、
抜け毛薄毛が気になる方で湯シャンによる抜け毛薄毛の改善効果を感じている方は、約半数だそうです。
私自身は、湯シャン中も普通に髪の毛は抜けますし、全体の毛量などに変化はさほど感じていません。
同じ頭皮や髪のケアという部類で言うと、私は湯シャンよりはヘナをしていた時の方が髪が強く元気になる
感じがしました。
次に私が感じているメリットも書きたいと思います。
個人の意見にはなりますので、どなたにも当てはまるわけではないと思いますが、参考にしていただければ
幸いです。
頭皮の環境改善が一番大きい効果
よく、頭皮がオイリーな方には湯シャンはあまり向いていないという意見を聞きますが、私は
オイリーで、それをどうにかしたいと思ってる方こそ緩やかに湯シャンを取り入れるのは良いと感じています。
私自身もオイリーな方で、湯シャンを取り入れる前は男性が主に使う皮脂をしっかり落とす効果のある
シャンプーを使用してしていました。
それでも、夕方には自分の頭皮の匂いが気になっていました。
でも、今は湯シャンがきちんと行えてる日は頭皮の匂いは気になりません。
逆に、シャンプーを連続して使っている時の方が、夕方皮脂の匂いが気になるという現象が起きます。
シャンプーで取り除きすぎた皮脂を補うために、過剰に油分が出てきているんだろうなと感じます。
上手に湯シャンが行えているというのがポイントにはなりますが、湯シャンで皮脂のバランスが整い、
頭皮環境が改善されているんだろうなと感じています。
かなりオイリーな方が、いきなり完全に湯シャンに移行するのは無理だと思いますが、湯シャンの日と
シャンプーをする日をバランスよく組み合わせながら、自分の皮脂状態を見つつ湯シャンを取り入れて
いくと良いのではないかなーと思います。
シャンプーの消費量が減る
シャンプーをする日が減りますから。
だから、たまにしか使わないシャンプーを上質なものに変えることも、どんどん減っていくわけじゃないので
あまり惜しむことなくできます。
デメリット
- ベタつきや匂いが残ることがある
- 整髪料が使えない
- 良い効果を感じるまでに時間がかかる
- 髪のツヤがなくなる
私の感じるデメリット
手間と時間が通常のシャンプーよりかかる
やり方②にあるように、湯シャンは5分程度時間をかけて丁寧に行う必要があります。
その分、お湯をたくさん使うことになります。
また、指の腹を使って頭皮を優しく揉むように洗っていくので、意外に握力が必要だったり、少し長めに
腕を上に上げているので最初のうちは腕が疲れたりしていました。
慣れてくると疲れなどは気にならなくなりましたが、時間はかかるので、私は旅先など自宅以外では湯シャンは
できないです。
この、丁寧にできているかどうかでその日の快適さが決まるので、今後も湯シャンが続けられるかという
モチベーションの変化にもつながります。
ツヤや良い香りがないのでちょっとつまらない
ここに関しては、湯シャンがかなり定着して上達してくると自然な自分の皮脂でツヤも出てくるというのは
聞いたことがありますし、香りもヘアコロンなどでつけたりと工夫はできます。
また、湯シャンを機にこう言った煩悩から離れるというのも良いのかもしれません。
しかし最初からは無理、何かこう虚しく寂しく、私はこういう姿を求めていたのだろうかとちょっと悲しくなった
記憶があります。
本当にかなり最初の頃です。
とにかく効果実感まで時間がかかる
私自身もまだ湯シャンという旅の途中にいるので、この先どんなところに辿り着けるのか、
どんな景色が見えるのか分かりません。
特に私は、他でも書いたように100%湯シャンにするのはまだ先で良いと思っているので、旅の進み具合も
ちんたらしています。
毎日、自分の髪や頭皮の状態に合わせてどういう洗い方をするか試行錯誤してる感じです。
しかしまずは、それまでのシャンプー生活で溜め込んだシャンプーの成分(シリコンなど)が落ちてしまえば
最初の段階はクリアなのではないでしょうか。
もしくは、髪をバッサリ切ったりと素の髪に生え変われば湯シャンもやりやすくなるし、効果も早く実感できる
ようになるのかなと感じています。
何を求めて(目指して)湯シャンを取り入れたいの
湯シャンのメリット、デメリットを踏まえた上で、では、どうして湯シャンを始めてみたいと思ったのか、
もっと言うと湯シャンに何を求めているのかと、どんな頭皮や髪の状態を望んでいるのかを明確にしてみると
自分なりの湯シャンの取り入れ方が少し見えてくるのではないかと思っています。
私の場合
私は普段、ヨガ講師として働いています。
接客業なので、周りに不快な匂いを感じさせたくないというのはもちろんですし、自分自身が
「匂ってたらどうしよう」と気にし続けるのもストレスになります。
また夏はかなりの汗もかきます。
さらにお客様に与える印象として、あまりにナチュラルな自然に任せたままのような、言ってみればボサボサな
状態も嫌ですので、ヘアオイルで髪を落ち着かせたり、髪が長い時にはまとめるために状況によっては
ワックスを使うこともあります。
そして、私は頭皮のオイルマッサージも大好きです。
オイルマッサージはある程度の量のオイルを使用しますから、マッサージした日にはオイルを落とすために
シャンプーをする必要があります。
そういった私の状況からして、100%湯シャンで生活というのは無理だなと思ったわけです。
ですが、髪はこれから先もできるだけ元気な状態でいてほしいし、何より量が減ってしまいたくありません。
扱いやすい、きれいな髪とそのベースになる健康な頭皮をずっと保っていきたいです。
同じように思う方は多いと思います。
そのために、湯シャンというのは有益な方法だと感じましたし、できるだけ自分の生活に取り入れたいと
思いました。
私の目的とスタイルに合わせた湯シャンの取り入れ方
上記のような目的と生活スタイルで、現在私が行なっている緩い湯シャンのやり方をお伝えします。
平日は、馬油や椿油で髪をまとめていることが多いです。
ちなみに、髪の長さは肩上のボブでブリーチをしてカラーを入れています。
汗のみなら湯シャンで流すこともできますが、オイルは落ちないため、クリームシャンプーで洗う日と、
髪のみにシャンプーを付けて洗う日、そして普通にシャンプーで洗う日を繰り返します。
その日の髪や頭皮の状態、使ったスタイリング剤などに合わせて、また、シャンプーする日が連続しない
ように、スタイリング剤が蓄積しないようにと言う観点で、どのように洗うかを選択します。
髪に触った感じだと、クリームシャンプーでもオイルは落ちていると感じますが、あまり過信しないように
しています。
シャンプーを使った日にはもちろんトリートメントも使用します。
普通にシャンプーで洗う日に合わせて週1回オイルで頭皮マッサージをします。
休日は、髪には何もつけないようにして湯シャンをします。
大体、週に2日湯シャンをするような頻度です。
シャワーヘッドを頭に当てて、シャワーのお湯がしっかり頭皮や毛穴に届くようにしながら時間をかけて
頭皮を揉むように洗います。
私は、40度辺りの少し高めの温度で洗います。
オイリーなのが気になる方は、少し高めの温度で洗っても良いのではないかと思います。
ただし、高すぎる温度で皮脂を落としすぎるのは要注意です。
また、湯船のお湯を捨てる日は、お湯の中に頭をつけて、お湯の中で頭皮をしっかり洗い最後にシャワーで
さらに流すということもしています。
過去にいろいろチャレンジして挫折したので今がある
初めて湯シャンにチャレンジしたのは、おそらく15年くらい前だと思います。
その頃の私は、髪はカラーはしていませんでしたが、セミロングくらいの長さだったと思います。
夕方の頭皮の匂いが気になって男性用かなりサッパリシャンプーを使っていました。
そこから、いきなりお湯のみで洗ってみたのですが、とにかくお湯を当てて指で髪を梳かそうとしても、
髪が絡まって指が全然通らないし、地肌に触れるのも難しいくらいでした。
それでも中途半端にしか洗えないというわけにはいかないので、ものすごく時間をかけて何とか
それなりに洗ってみたものの、終わった時はスチールウールのように、髪が今まで見たことのないような
絡まり具合になっていました。
それを数日続けては挫折しを繰り返していました。
試行錯誤の日々
ある時インドのハーブの粉を使ってシャンプーをすると良いというのを見て、取り寄せ試してみました。
数種類のハーブの粉を水に溶かし、その液体をお好み焼き屋さんにあるマヨネーズを入れてる容器のような
口が細くなっているボトルに入れて、直接その液体を頭皮にかけて洗うというのをやってみました。
ハーブ粉は完全に水に溶けるわけではないので、言ってみれば底に砂のような物が沈澱した茶色い泥水の
見た目のまさに土臭いような匂いのする液体で髪を洗っていると、当時の私はまだ若かったので、
本当に本当に虚しくなったのを覚えています。(こうやって書きながら、今ならいけるかもとも思いました)
それで洗ってもまだサラサラになるわけでなく、良い香りも当然せず、スチールウールの仕上がりに
自分が何を求めてこういうことをやっているのかわからなくなっていました。
今思えば、髪にそれまでのシャンプー生活で溜め込んだシャンプー成分が邪魔をしていたんだと思います。
さらに髪も長かったので本当に大変でした。
その後も、酢やクエン酸でリンスをしてみたり、西洋のハーブを漬け込んだ液体を作ってみたりと様々な
これは良いと聞いたことを試してきました。
自分で作った石鹸で洗うというのもやったりしました。
あまりに酷い仕上がりからなかなか抜け出せないので、何かやり方を間違えているのかと思い、
数冊書籍を購入して勉強したりもしました。
少しずつ見えてきた自分の理想の姿
転機になったのは、髪を切ってショートにした事で、それまで邪魔をしていた成分が付着していた髪が
なくなった時からだと思います。
髪も短くなって洗いやすくなり、髪が絡まる事なく湯シャンが続けられるようになりました。
ただ私の場合は、1週間2週間と続けていくと、ツヤがない、整髪料が付けられない、皮脂の匂いはしないが、
自分の中から発する私の匂いみたいなものが気になって、試行錯誤しながら今のやり方に辿り着いた
感じです。
色々やってみて、湯シャンを始めたからといって俗世の便利なものから全て離れてナチュラルに生活して
います、のような姿になることを望んでいる訳ではないんだなと気付きました。(私の勝手なイメージです)
特に私は癖毛でもあるので、湯シャンで素のままのショートにしておくと、より一層何もしていない人のように
見える気がします。
現在の私の髪の状況
上記のやり方で、今私は週に1〜2日シャンプーをし、2日は湯シャンをし、その他はクリームシャンプーなど
穏やかな洗い方で数年過ごしていますが、匂い、手触り、ツヤ、そしてカラーの色持ちと全てに満足しています。
ただそれは、丁寧な湯シャンや洗い方がきちんと出来ていたらで、疲れて面倒だったりスケジュールの関係で
シャンプーする日が連続してしまったりすると、いつもより頭皮が乾燥してるのが分かり、夕方の頭皮の匂いが
気になるようになります。
シャンプーで皮脂を取り去り過ぎて乾燥した頭皮に、過剰に皮脂が分泌されているという事ですね。
洗いすぎてるという事と、丁寧な湯シャンの大切さを感じます。
また、ヘアカラーはシャンプーをする時にカラーが落ちていきます。
今までシャンプーをしていた頃は、何色に染めても時間が経つと最終的にいつも同じ黄色っぽい色に
なってしまうのが嫌だったのですが、湯シャンと時々使う紫シャンプーで染めた時の色が保てているのも
嬉しいです。
ゆっくりでいいし完璧じゃなくても良いと思う
私は、いずれ今の仕事を辞めて人前に出る機会が減ったり、整髪料を使わなくてもよくなった頃に完全な
湯シャンに移行できたらと考えています。
それまでは、今の生活スタイルや自分のこうありたいという気持ちをを大切にしたいと思います。
今の自分が幸せで快適であるという事をいつも一番に考えます。
湯シャンに興味を持ってここまで読んで頂いた皆様には、正しいか間違っているかだけではなく、
何を望んでいるのか、日々が快適かどうかということも意識しながらご自分なりの湯シャンを取り入れて
もらえたらいいなと思います。
これから先、まだまだたくさん髪を洗いますし、何よりあなたの体、髪の毛なのですから。
私も、今回こうしてブログを書きながら過去の事を思い出してみて、今ならインド式シャンプーに
チャレンジできそうな気がするので、もう一度インドハーブを取り寄せて試してみたいと思いました。
また、クリームシャンプーの選び方についても詳しく知りたいと思ったので、今後ブログに書きたいと
思います。
ここまで読んでいただきありがとうございました!